-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2026年2月 日 月 火 水 木 金 土 « 1月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
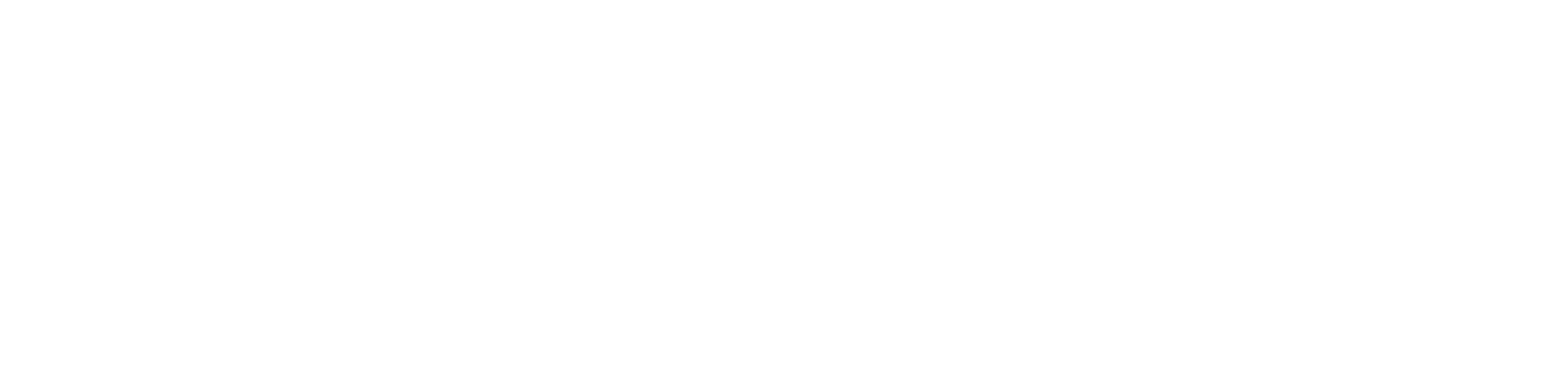
皆さんこんにちは!
株式会社名取工業、更新担当の中西です。
1️⃣ Rを作る三手法
1) 合板曲げ:ケガキ+切り欠き(ケーフィング)or湯湿し曲げでR形成。小Rは薄合板の積層が安定。
2) セグメント化:多角形分割でRを近似、パテ処理で面を整える。大R・長尺に適す。
3) 既製Rパネル/型枠ライナー:仕上げ優先や繰返しに強い。コストと納期のバランスを。
2️⃣ 設計の勘所
• 最小曲げ半径:合板の曲げ限界を超えると割れ・反りが発生。薄板多層+内側当て木で補強。
• 目地とPコン:Rの中心角で等分割し、コーン跡が光の反射で乱れない配置に。
• 連続R:柱→梁→壁の“つなぎR”はケラバ(小端面)の納まりを先に決める。
3️⃣ 組立と保持
• 押し型/引き型:R外側=押し型で当て木密、内側=引き型でワッシャ増し。
• 補強:R直交方向に肋材、端部はクランプ+通しセパで“開き”を抑制。
• 離型剤:塗りムラが光で強調されるため、霧吹き→拭き上げを徹底。✨
4️⃣ 打設・解体のコツ
• 流れ:R内側は気泡滞留しやすい。細径バイブで短時間多点、打重ねは浅く。
• 解体:面を滑らせるように剥がし、こじらない。端部から順に。
• 補修:光沢差が目立つため、試験補修を先行。
5️⃣ チェックリスト✅
☐ 最小曲げ半径を守ったか(薄板多層で回避できるか)
☐ Pコン・目地割を中心角等分で整えたか
☐ 肋材・通しセパで端部開きを抑えたか
☐ 打設手順と細径バイブを共有したか
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社名取工業、更新担当の中西です。
1️⃣ 階段の“歩行感”を決める黄金則
設計寸法は与えられますが、仕上げ厚(タイル・長尺シート・塗床)や巾木、天端モルタルで実際の歩行感が変わります。一般的に蹴上げ(R)×2+踏面(T)≒ 600〜640mmが歩幅に近くて歩きやすい目安。現場では仕上げ込みでのR/Tを必ず逆算。
2️⃣ 墨出しと基準段
• 基準段:1段目を踏面先端(ノーズ)基準で設定。タイル見切り分を0段目で吸収。
• 勾配治具:R/Tから起こした勾配を合板治具にして、側板へ連続移し。
• 踊り場:レベル見切りを明確にし、段割の端数は上部で吸収するのが原則。
3️⃣ 型枠構成
• 側板:R/T墨を通し、ノーズ位置に面木orアール見切り。
• 踏面板:転用合板は補強リブを多めに。蹴上げ板との取り合いに当て木。
• 手摺下地:インサートは蹴上げ位置から規定高さ、連通性を確保。
• 排水勾配:外部階段は踏面1/100〜1/50の微勾配を“面”で作り、水溜りゼロへ。
4️⃣ 打設と仕上げ
• 打設方向:下から上へ層状。バイブは短時間、段鼻に気泡が溜まりやすいので細径を多点挿入。
• 天端仕上げ:踏面はコテ当て回数を最小にして粉吹き・色ムラを回避。
• コーナー保護:段鼻保護材を解体前に貼り付け。️
5️⃣ ありがち不具合→対策⚠️→✅
• 段差バラツキ:基準段の誤差。→0段目で吸収、勾配治具の共通化。
• 段鼻欠け:解体時の衝撃。→角養生+解体順序(蹴上げ板→踏面板→側板)。
• 気泡跡(豆板):段鼻下の空気溜まり。→細径バイブ+軽打ち、逃げ穴を検討。
6️⃣ チェックリスト✅
☐ R/T×仕上げ厚で歩行感を逆算したか
☐ 基準段=踏面先端で統一したか
☐ 段鼻保護と角養生を解体前に実施したか
☐ 手摺インサートは位置・レベルが合っているか
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社名取工業、更新担当の中西です。
1️⃣ まず“5点合わせ”を現場語に翻訳
設備・躯体取り合いの失敗は、情報の粒度差から生まれます。施工図の「中心・高さ・下端・見付・ピッチ(数量)」を、型枠で作る線と治具へ落とし込みましょう。
– 中心:通り芯からの左右オフセットを“赤”、高さは“青”など色分けで誤読防止。
– 下端/上端:仕上げ厚・勾配・モルタル天端を差し引いた躯体基準へ変換。
– 見付:見切り材・額縁見付・カバー範囲とPコン・目地割を合わせる。
– ピッチ/数量:孔あけテンプレートを作り、採寸→マーキング→孔あけを“1セット化”。📏
2️⃣ スリーブの設計と固定🧰
• 材質:塩ビ・鋼管・紙管・発泡スリーブなど。火気・防火区画・防水要求で選定。
• 固定:
o 壁:二重枠+内側受け当て、外側は番線結束+当て木。開口集中部は増しセパ。
o スラブ:根太に吊りバンド、抜け止めピンで“浮き”を防止。
• 端部処理:紙管は離型剤の染み込みで剥離不良に注意。端面シール+保護テープで養生。
• 偏芯対策:テンプレートは通り芯に“ツノ”(直角治具)を付け、ひと目で直交確認できる形状に。🧩
3️⃣ 大開口・サッシまわりの“二重枠”と補強
• 二重枠:仕上がり寸法=サッシ外形+クリアランス(例:±6〜10mm)の“外枠”、躯体端部に当て板+補強リブ。
• コーナー補強:斜めリブ+通しセパで“はらみ”を制御。
• 水止め:外壁は水返し段差や止水材(止水シート/止水セパ)を型枠側で確保。💧
4️⃣ インサート・アンカーの埋設🎯
• 配置ルール:梁・柱主筋との干渉回避が最優先。鉄筋屋と事前合意し、“NGゾーン”地図を現場に掲示。
• 固定:マグネット治具や合板裏当て皿で位置決め。締結方向(捩れ)に注意。
• 抜け止め:重量物吊りは把鉤長・コンクリート付着長の根拠を残す。📸
5️⃣ 施工手順(壁開口の標準)
1. 墨出し:外枠→内枠→インサート→セパ割の順で上から下へ。
2. 補強:コーナー・梁下・端部に当て板+外控え、セパ1サイズ密。
3. スリーブ固定:テンプレートで孔位置一括→差し込み→結束。
4. 写真:通り・レベル・スケール入りで“誰でも再現”できる角度。
5. 打設:開口下から対角・層状に、過振動禁止。
6. 解体:縁欠け対策に角養生材を使用。
6️⃣ トラブル→是正⚠️→✅
• スリーブの浮き・傾き:結束不足。→吊りバンド二重化、抜け止めピン追加。
• 漏れ:紙管端部からのしみ出し。→端面シール+パッキン、目止め。
• 位置ズレ:テンプレート誤差。→通り芯“ツノ”治具で直交確認を標準化。
7️⃣ チェックリスト✅
☐ 5点合わせを色分けで現場見える化したか
☐ 二重枠・増しセパを開口集中部に入れたか
☐ NGゾーン地図を鉄筋・設備と共有したか
☐ テンプレートは通り芯基準で固定したか
☐ 写真は再現性重視の画角で残したか
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社名取工業、更新担当の中西です。
1️⃣ 役割と種類(まず“目的”から)
• 役割:対向する型枠の間隔保持+側圧抵抗。意匠面ではPコン跡の配列が美観を決める。
• 種類:
o コーン式:撤去容易、打放し向き。コーン径・深さで補修リスクが変わる。
o スリーブ式:止水性/防水納まりに強い。シーリング/止水材とセットで設計。
o 一体式/貫通:止水セパ(PC鋼棒+止水板)など。地下外壁など水圧を受ける部位に。
2️⃣ ピッチ設計(側圧×面材×根太)
• 基本:側圧p(kPa)に対して、面材厚・根太間隔・締結力で決める。
• 経験則:壁厚200mm・高さ3.0m・通常打設で、@450〜@600が目安。高スランプ/低温/高速打設なら@300〜@450へ。
• 開口周り:1サイズ密(例:本体@450→開口周り@300)。角は通しセパ+当て木で“はらみ”抑制。
• 端部・コーナー:引張力の逃げ場が少ないため増しセパ。ターンバックルで微調整。
3️⃣ 打放し意匠とPコン割付
• ルール決め:目地・Pコンを同一グリッドに。サッシ・手摺・照明のレイアウトと“重ねる”と美しい。
• 標準割:縦@600×横@600が基準。スパンや梁下端での“割り切れ”に注意。
• 補修計画:コーン穴の補修色を試験打ちで確定。季節/骨材で色味が変わる。
4️⃣ 締結力と施工性
• ナット締付:均等締め(対角→周回)。増し締めタイミング(打設前/打設中の休止点)を明文化。
• 座金/ワッシャ:面圧分散。面材のめり込みを防ぐ。
• 施工性:片側作業になる場合はスリーブ式が有利。両側アクセス可ならコーン式の自由度。
5️⃣ 防水納まり(地下・外壁)
• 止水セパ:止水板一体型を使用。継手処理はメーカー仕様書+現場モックで確認。
• シーリング:躯体打設後の収縮を見越し、追従性の高い材料を選択。
• 雨天打設:コーン穴への雨水侵入を防ぐ養生キャップを標準化。️
6️⃣ トラブル事例→対策⚠️→✅
• コン抜け/緩み:締結不均等・ワッシャ欠落。→対角均等締め、ダブルチェック。
• 漏水:止水処理不足。→止水セパ+二次シール、水張試験を計画。
• 錆跡:切断面露出。→防錆塗布、切断長の統一で管理。
7️⃣ 明日から使えるチェックリスト✅
☐ 側圧条件(高さ・速度・温度・スランプ)を朝礼で共有したか
☐ 開口/コーナーは1サイズ密にしたか
☐ Pコン割は目地・サッシと整合したか
☐ 止水セパ/二次シールの要否を判断したか
☐ 増し締めのタイミングを工程に入れたか
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社名取工業、更新担当の中西です。
1️⃣ 支保工設計の原理原則
• 荷重の見える化:自重+新設コンクリート+作業荷重+施工機材。集中的な荷重点(柱頭・梁下)を特定。
• 伝達の“連続性”:面材→根太→大引→サポート→ベース→地盤。どこか一箇所でも弱いと全体崩壊。
• 座屈と座金:サポートは伸ばし切り厳禁、座金は敷板+くさび固定で回転防止。
• 地耐力:地組みはベースプレート+敷板、埋戻し直後は沈下リスクに注意。
2️⃣ 足場と作業床(安全は生産性)
• 先行手摺・先行床:墜落リスクを元から排除。段取り8割の象徴。
• 通路計画:人・資材・クレーンの動線分離。交差部はゼブラ養生で注意喚起。
• 腰痛対策:持ち替え回数削減(大判化・台車化)と荷姿統一が最強の対策。♂️
3️⃣ 倒れ止め・控え・ブレース
• 外控え:壁型枠は3〜4mピッチで控え、コーナー・開口周りは増し控え。
• ターンバックル:レベル・通りの微調整に有効。締付帳票で点検を見える化。
• 風荷重:高所・開放面は風速10m/s超で作業停止判断基準を明文化。️
4️⃣ 再支保(リショアリング)の勘所
• 目的:早期解体で回収した支保工を再配置してたわみ・ひび割れを防止。
• 手順:解体→再支保→上階打設→段階解放。解体順序と下階の受けを工程に織り込み。
• 注意:偏荷重が出やすいため、大梁直下は密に。
5️⃣ 点検・記録・是正
• 日常点検:朝礼前に緩み/くさび/座屈/沈みを指差し確認。
• 帳票:是正箇所・担当・期日を残す。写真は全景+アップの2枚セット。
• 地震後:日本の現場では余震点検の標準化が重要。
6️⃣ よくある事故と未然防止⚠️→✅
• サポート抜け:伸ばし切り+振動で抜け。→短いサポートを継ぎ足し、くさび二重。
• 倒れ:開口集中+外周部の控え不足。→角で控え増し、風の見張り番を置く。
• 沈下:埋戻し上に地組み。→敷板増し、養生日数の遵守。
7️⃣ 明日から使えるチェックリスト✅
☐ 荷重の流れ(面→根太→大引→サポート→地盤)が切れていないか
☐ サポートは伸ばし切りゼロか
☐ 控えピッチ/増し控えが図面化されているか
☐ 再支保計画が工程表に織り込まれているか
☐ 点検結果が写真+帳票で残っているか
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社名取工業、更新担当の中西です。
1️⃣ 比較軸の設定(現場は“総合点”で決める)
• 精度(寸法・通り・面)
• 生産性(m²/人日、タクト日数)
• 安全性(先行手摺・作業姿勢・持ち替え回数)
• コスト(初期投資・転用回数・補修)
• 搬入性(重量・部材点数・クレーン依存)
• 意匠適合(打放し・目地・R対応)
2️⃣ 壁型枠の選択肢
• 在来合板:自由度◎。曲面・局所補強が容易。化粧面は厚め+支持密が鉄則。
• 鋼製/アルミパネル:精度・転用◎。Pコン・目地割は設計段階で確定を。
• クライミング型枠:高層・同断面繰返しに強い。風対策とアンカー計画が要。
• 打放し専用パネル:目地・コーン跡の意匠ルールを先に決め、材料と一体設計。
3️⃣ スラブの選択肢
• 在来支保工+合板:どこでも対応、小梁多でも自在。解体手間は多め。
• システム支保工(ドロップヘッド):早期解体→資材回転◎。再支保(リショア)の計画が前提。
• デッキプレート:常用化された軽量化手段。打継ぎ・山上/谷上の納まりに注意。
• 大判パネル:面精度・歩掛アップ。吊荷管理と保管スペースの確保が鍵。
4️⃣ 梁・柱の選択肢
• 梁:下型は根太大引の“荷重の道”設計、側型はハンチ・段差の型板精度が肝。
• 柱:角柱は四隅の締結均等、円柱はR型枠/分割。化粧柱は目違いゼロの管理。
5️⃣ 選定フローチャート
1. 繰返し度(高→低)
2. 意匠制約(打放し・R・目地)
3. 搬入制約(クレーン/養生スペース)
4. 工期とタクト
→ 繰返し×意匠×搬入でマトリクス評価し、“一体最適”より“全体最適”。
6️⃣ ケーススタディ(中層RC・住棟)
• 外周壁:鋼製パネル+クライミング台
• 戸境壁:在来合板(開口多・変更多に柔軟対応)
• スラブ:システム支保工(ドロップヘッド)+早期解体→再支保
• 梁・柱:梁は在来、柱は鋼製パネル
→ 結果:タクト2日短縮、打放し面補修70%削減、搬入回数20%減。
7️⃣ 明日から使えるチェックリスト✅
☐ 繰返し度と意匠制約を数値化(★1〜5)したか
☐ Pコン・目地割を設計段階で確定したか
☐ 再支保計画を工程表に織り込んだか
☐ 搬入/保管スペースを図面に落としたか
☐ 試験打ち/モックアップの可否を判断したか
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社名取工業、更新担当の中西です。
1️⃣ 図面を“優先順位”で読む
型枠は設計意図の実体化。したがって図面の読み方は、単に寸法を拾う行為ではなく、どの情報を優先するかの判断です。基本の優先順位は次のとおり。 1. 構造図の基準(通り芯・GL・スラブレベル・打継ぎ位置)
2. 意匠図の仕上げ基準(見付・見切り・割付・アール)
3. 設備図の貫通・インサート・スリーブ位置
4. 施工計画書(型枠支保工計画・搬入計画)
→ 矛盾は必ず起きる前提で、職長は「どの基準に寄せるか」を最初に宣言しておくのが肝。
2️⃣ 墨出しの準備(測量・基準確立)
• 一次基準:ゼネ側基準点(BM)・通り芯の受領確認。受領書式に“誰から・どこで・何を”明記。
• 二次基準:各階で増設BM(柱・壁に釘+ペイント)、仮BMは原則使い捨て。
• 機器:オートレベル/トランシット/レーザー。気泡管ゼロ点・気温順応(10〜15分)をルール化。
• 誤差源:脚頭の沈み、三脚の緩み、受光器のオフセット、温度伸縮(鋼尺は日向NG)。
3️⃣ 墨出しの手順(基本)
1. 通り芯を確定:外周で“□”を閉じ、対角長で整合(差は±3mm以内が目安)。
2. レベル墨:GL=±0の基準を壁/柱に複数箇所。階ごとに+1,000mmの見やすい基準も併記。
3. 型枠外面ライン:コンクリート躯体寸法から面材厚・見切り材厚を差し引き。
4. 開口・スリーブ・インサート:施工図の“5点合わせ”(中心・下端・高さ・見付・ピッチ)を現地に変換。
5. 写真記録:スケール・通り表示・レベル墨・指示書を同一画角で。
4️⃣ 応用——階段・R壁・斜め壁の墨
• 階段:基準段(1段目)を“踏面先端”基準で描く。蹴上げ補正(仕上げ厚・塗床)を忘れない。
• R壁:芯半径→型枠外面半径へ補正。分割角度=パネル有効幅/円周で割付。
• 斜め壁:傾斜角θの鉛直投影を先に決め、セパの直交性が崩れないよう治具を用意。
5️⃣ 墨出し台帳(再現性の鍵)
• 項目:日付/階/通り/基準点/BM高/使用器材/気温/担当/確認者/誤差補正。
• ルール:“測る人”と“書く人”を分ける、昼休み/打設後に再測、消える墨は即保護。
6️⃣ 失敗→是正の定石
• 通り芯ズレ:両端で±5mm以上ならどちらに寄せるか監督と即決。芯ズレ吸収のため二重枠。
• レベル段差:天端化粧部は±3mm以内、非化粧は±5mm以内を目安。天端型枠の押さえを増し。
• 開口位置違い:型枠内から見える化(赤スプレー・タグ)。前日/当日でダブルチェック。
7️⃣ 明日から使えるチェックリスト✅
☐ 通り芯は対角寸法で照合したか
☐ レベル墨は複数の壁/柱に残したか
☐ 仕上げ厚・見切り材厚の差し引きは反映済みか
☐ 階段は踏面先端基準で描いたか
☐ 開口・スリーブの5点合わせを現場共有したか
☐ 写真は根拠が写る角度で撮影したか
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社名取工業、更新担当の中西です。
1️⃣ なぜ側圧を読むのか
打設中のコンクリートは流体+粒体。単位体積重量γ(おおむね23kN/m³)と高さh、打設速度v、温度T、スランプSが側圧に影響します。読み違い=はらみ・漏れ・倒壊に直結。📊
2️⃣ 基本イメージ(簡易)
• 静水圧モデル:p ≒ γ × h(kPa)。例:h=3.0m → p≒23×3=69kPa。
• 実務では打設速度が遅いほど内部の“見掛け粘性”が上がり、圧力は低下。逆に高速打設+高スランプ+低温は圧力が高めに出やすい。
• 安全側に読むのが原則。📐
3️⃣ 設計の要点(壁・柱)
• セパピッチ:水平/縦の間隔を圧力・面材厚・根太剛性で決定。開口周りは1サイズ密に。
• 補強リブ:荷重の“逃げ道”。コーナー・T字・L字は外控え+内当て木で剛性UP。
• 柱型枠:梁スリーブや添え筋で“偏荷重”が出やすい。四隅の締結均等化が肝。
• 打設計画:層ごとの止め位置(“止め梁・止め壁”)を決め、バイブ挿入パターンを共有。
4️⃣ スラブ・梁・支保工
• たわみ:許容たわみ(L/500など)を目安に根太ピッチ・大引間隔を設定。
• 再支保(リショアリング):解体後の荷重再配分を計算に入れる。解体→再支保→次打設のタクトを。
• 柱頭・梁下:荷重集中に“受け広げ”の当て板を標準化。🧱
5️⃣ 施工中の合図を読む👀
• 鳴き音/きしみ:締結不足のサイン。すぐ増し締め。
• 微小な漏れ:大きな漏れの前兆。速やかに目止め+控え増設。
• 面の振動波:過振動。バイブ停止→位置変更。
6️⃣ 打設速度・スランプ・温度の合わせ技🧪
• 高スランプ(流動性高)+低温(硬化遅い)+高速打設=最大圧力に近づく。
• 暑中は逆で側圧が下がりやすいが、打継ぎ・コールドジョイントのリスク増。→タクト短縮+増員で対応。
7️⃣ 数字を“現場語”に翻訳する🗣️
• “この壁は3mだから70kPa級。セパは@450→@300に、開口周りは@250で。”のように、数式→ピッチと金物の指示に落とすのが職長の仕事。
• 写真管理は、セパピッチと増し控えの“根拠”が写る角度で。📸
8️⃣ 即使える簡易手順✅
1) 高さ・打設速度・スランプ・温度を当日朝に再確認。
2) セパピッチ/補強を“高側圧想定”で指示。
3) 開口・コーナーは二重枠+外控え増しで先手。
4) 打設は対角・層状、バイブは短時間・多点。
5) サインを感じたら(鳴き・漏れ)即止め→是正。
9️⃣ まとめ
側圧は“想像力の学問”。数字を根拠に、現場の音・手触り・流れを読む。次回は図面と墨出しで、狂いを生まない前工程の作法を解説します。🧭
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社名取工業、更新担当の中西です。
1️⃣ 合板(コンパネ)の基礎
• 厚みと支持間隔:12mm/15mm/18mm。支持間隔を詰めるほど反り・たわみは減るが手間増。仕上げ重視なら厚め+支持過密が鉄則。
• 表面:フィルム面(メラミン/フェノール)→離型性○・打放し○。木口の防水処理で寿命が大きく変わる。
• 等級/JAS:節・色ムラ・表面平滑性。打放しや化粧面は上位等級を選定。
2️⃣ 鋼製/アルミ型枠
• 強み:寸法安定・繰返し転用◎・面精度◎。Pコン跡/目地の計画と意匠調整が肝。
• 弱み:初期投資・重量・仮設荷重。クレーン段取りと保管スペース計画必須。
• 使い分け:外周壁・共用部=鋼製/アルミ、複雑意匠=木製カスタム。
3️⃣ セパレーター/フォームタイ(Pコン)
• 機能:対向する型枠の間隔保持+耐圧。
• 種類:スリーブ式/コーン式/一体式。仕上げ(打放し・防水)や撤去性で選ぶ。
• ピッチ:打設速度/コンクリート温度/スランプで圧力が変動。安全率を見込む。
• 開口周り:増しセパと補強リブで“はらみ”を抑制。
4️⃣ 支保工・サポート・クランプ類
• パイプサポート:許容荷重と座屈長。伸ばし切り厳禁、短いものを組み合わせて剛性UP。
• 単管/クランプ:盛り替え時は対角ラチェット増し締めが基本。
• 根太/大引:荷重伝達の“道”。荷重集中箇所(柱脚・梁下)にあて木+受け広げ。
5️⃣ 離型剤(剥離剤)
• 油性/水性/ハイブリッド:仕上げ・環境・季節で選ぶ。塗り過ぎ=色ムラ・はじきの原因。霧吹き塗布+拭き上げをルール化。
6️⃣ 金物・消耗品
• 番線は太さとねじり回数で保持力が激変。ねじりすぎは金属疲労。
• くさびは再使用で痩せる。定期交換+刻印で寿命管理。
• パッキン/気密テープは開口・打継ぎの漏れ止めの生命線。
7️⃣ 調達と保管のコツ
• 転用設計:図面段階で“何回使うか”を決めると、等級・厚み・表面処理が自動的に決まる。
• 保管:端面シール+養生フィルム+水平保管。立て掛けは反りの温床。
• 清掃:解体後即清掃→離型剤薄塗り→次工程への“即時回転”が寿命を伸ばす。
8️⃣ 失敗あるあると回避策♂️→✅
• 安物買いの銭失い:仕上げ面でやり直し→原価爆死。→化粧面は上位材+試験打ち。
• 離型剤ダレ:ムラ・はじき。→薄塗り・二度塗り禁止・拭き上げ。
• セパ短すぎ:締め代不足→はらみ。→支給長さ+カラーで即識別。
9️⃣ まとめ
材料は“投資”。寿命×手直し削減×美観で総合最適を。次回はコンクリート圧力と型枠強度の勘所を、数式と現場感覚の橋渡しで解説します。
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社名取工業、更新担当の中西です。
1️⃣ 型枠工事のミッション
コンクリートという“流れる材料”を、設計者の意図どおりの形・寸法・表面品質に“翻訳”するのが型枠工事の使命です。翻訳が甘いと、はらみ・漏れ・豆板・寸法誤差・通りの狂い・レイタンス跡・ジャンカなど、躯体の品質と工期・原価に深刻な影響が出ます。型枠は単なる一時的な器ではなく、構造体の精度と美観、さらには建物の寿命まで左右する“影の主役”。ゆえに、段取り・納まり・安全・原価の四輪を噛み合わせる現場力が要求されます。💡
2️⃣ 全体フローと関係者
• 設計→施工計画(型枠支保工計画書・工程・タクト)→資材手配→地組/現場組→墨出し→組立→チェック→コンクリート打設→養生→解体→清掃・転用→次サイクル♻️
• 関係者は、型枠/鉄筋/設備/電気/ポンプ/生コン/監督/検査が主。取り合いの調停役は多くの場合、型枠職長。“開口・スリーブ・インサート・打継ぎ位置・目地・Pコン位置”は、最小の打ち合わせ漏れが最大の手戻りに化けます。🤝
3️⃣ 型枠の基本機能(3つの視点)
• 形状付与:図面どおりの形・寸法・面を作る(意匠・機能)
• 耐圧:打設時の側圧・振動・衝撃に耐える(構造)
• 作業基盤:足場・通路・手摺・工具置きなど作業性(安全) この3つのバランスが崩れると、どこかで帳尻合わせが起き、事故や不具合の温床になります。⚖️
4️⃣ 現場のKPIと管理軸
• 出来形:通り/レベル/寸法/面の平滑さ・色ムラ
• 生産性:m²/人日、1スパン当たりのサイクル日数
• 転用回数:合板・鋼製枠・セパ・支保工の寿命
• 安全:KY実施率・是正数・腰痛/挟まれゼロ
• 原価:材料歩留まり、手待ち削減、打設リードタイム⏱️
5️⃣ 失敗はどこから来る?——“3つのズレ”
1) 図面と現場のズレ(開口・段差・目地、配筋や設備と干渉)
2) 計画と実行のズレ(段取り・人員・資材・クレーン手配)
3) 時間と品質のズレ(打設速度・温度・スランプに対する耐圧余裕不足)
→ 対策:初期に“5点合わせ”(打継ぎ・開口・インサート・Pコン・目地)を合意、干渉はBIM/型板展開で見える化、当日変更に備えて“代替案”と余裕材(予備セパ・補強材)を標準装備。🧭
6️⃣ 明日から使えるチェックリスト✅
☐ 型枠支保工計画書は“図・根拠・責任者”がセットか?
☐ 壁・柱のセパピッチは打設速度/スランプ/温度を踏まえたか?
☐ 開口周りは二重枠・補強・躯体目地と整合?
☐ 通り芯・レベルは“他工種基準”と合わせたか?
☐ 離型剤は材料と仕上げに適合、塗布量は規定内?
☐ 先行足場・手摺は作業半径と搬入動線に合致?
☐ 写真管理は“根拠が残る角度”で撮る段取り?📸
7️⃣ よくある不具合と即効リカバリ🛠️
• はらみ/漏れ:開口・継手にパッキン/目止め。内側に当て木+外側控え増設。
• 通り狂い:基準通り芯から再測量、クサビ解放→再緊結。
• 豆板/ジャンカ:開口下端に逃げ穴、打設姿勢/バイブ入れ替え、打継ぎ計画の見直し。
8️⃣ まとめ
型枠は“段取り8割”。手戻りをゼロに近づけるのは、前工程での対話と見える化。次回は、現場で迷いやすい材料・資材の良し悪しの見極めを深掘りします。🔍
![]()